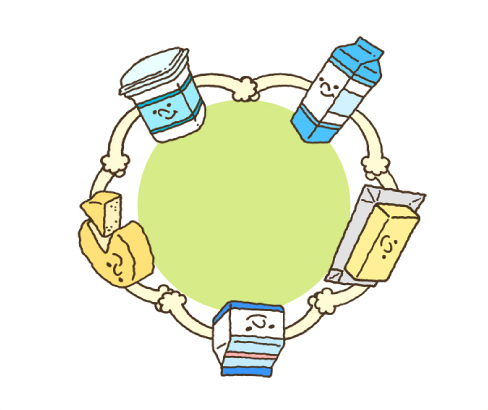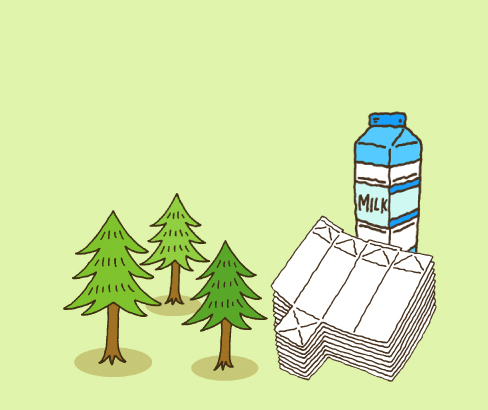- はじめに -
私と牛乳とのかかわりは、この「ファッションフード、あります。」の参考資料として「病気にならない生き方」という健康本を読んだのがきっかけでした。

「病気にならない生き方」は、現代の西洋化した食生活や加工度の高い食品を否定するという、よくある内容ですが、当時、100万部超えのベストセラーになりました。その中で一番過激だったのが牛乳否定です。牛乳を徹底的に批判していることで話題になった本でした。
それまで私は、牛乳は体にいいと素朴に信じていたので、牛乳が体に悪いという言説があることに驚愕しました。それから牛乳のことを調べるようになって、その過程で、牛乳ほど褒められたりけなされたりの落差が激しい食品はほかにはないのではないかと考えるようになりました。今でもインターネットで「牛乳」で検索すると、“牛乳は超危険”といったようなアンチミルク説がたくさん出てきます。
どれもほぼ同じ内容で新鮮味はありませんが、特徴的なのは、「私たち日本人は牛乳が体によいと洗脳されて強制的に飲まされてきた」と、みな怒っていることです。
非常に感情的な言説が多く、一見、科学的な根拠で裏づけてはいても、ちょっとそこまではあり得ないだろうというような、トンデモな話が多いです。
生活習慣病もガンもアレルギーも、あらゆる病気の諸悪の根源は牛乳であるような扱いをされています。
その一方で、牛乳は体によい健康食品であると説くサイトも非常に多いです。
こと牛乳となると、みなどうしてこんなに熱くなるのか。牛乳が本当にいいか悪いかはともかくとして、牛乳が導入されてからの150年の毀誉褒貶(きよほうへん)を追っていくだけでとてもおもしろかったのです。
その150年を1時間でお話しするのが、今日の私のミッションです。
牛乳は近代最初のスーパーフード
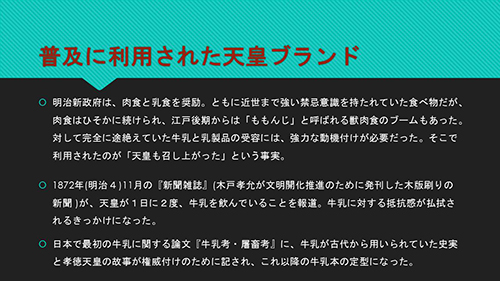
- 普及に利用された天皇ブランド -
ご承知のように、文明開化は“イコール西洋化”でした。まず何よりも、欧米人を初めて見た幕末のサムライや公家は、あまりにも体格が違うのにショックを受けたのでしょう。当時の成人男性の平均身長は155センチ前後だったので、190センチの大男だったペリー提督より頭ひとつ小さい。大きければよいというものではなくても、そこまで違うと屈辱的です。
食べるものが余りにも違いすぎる。肉を食べ、牛乳を飲まなくては強くなれない。そう危機感を抱いた明治新政府の指導者たちは、食の脱亜入欧=西洋化に着手して、それまで禁じていた肉を食べて牛乳を飲むことを国策として進めました。
肉は675年の肉食禁止令以降も密かに食べられていたので、比較的すんなりと受容され、あっという間に牛鍋ブームが起こりました。
それに対し、乳製品の文化は完全に途絶えてしまっていたために、抵抗感がはるかに強かった。牛乳は牛の血液とみなされたため、血をけがれとする意識の強い日本人にとって、なんとも気味の悪い、とても容易には受け入れられそうもないものでした。
そこで利用されたのが「天皇」というブランドです。
早くも明治4年11月、天皇が牛乳を1日に2度飲んでいることが、「新聞雑誌」という木版刷りの新聞に報道されました。今でも宮内庁御用達と聞くと付加価値がつきますが、当時のお上は神様ですから、今とは比べものにならない力があります。
その人が牛乳を飲んでいるという事実が、牛乳に対する強い抵抗感を払拭する理由づけとして使われたわけです。
天皇は西洋化のシンボルでした。牛肉を食べたのがその翌年の明治5年1月、洋服を着用したのが同じ年の5月、断髪したのが明治6年の3月ですから、牛乳飲用は一番早かったわけです。
また、新政府は、牛乳を奨励するキャンペーンの一環として、明治5年、国学者の近藤芳樹に「牛乳考・屠畜考」という書物を書かせました。
これが日本で最初の牛乳に関する論文です。この論文で何より強調されているのが、古代の日本で善那という渡来人が孝徳天皇に牛乳を薬として献上したことと、それ以降に皇族に愛用されてきたという故事でした。
この「牛乳考」以降、牛乳を奨励する書物や雑誌の記事には、この故事が権威づけに必ずと言ってよいほど使われるようになっています。
この「牛乳考」は、「牛乳は最上の良薬で、常にこれを飲んでいると、弱い人は強くなり、老人が成年に若返る」と、薬としての効果の説明で始まっています。そして最後は、「牛乳がけがれていないことは明らかなのだから、疑う心を捨てて飲んでみなさい、虚弱や老衰に効くことがすぐにわかる」と終わっています。
この本は、牛乳の滋養強壮効果とアンチエイジング効果を力強く保証しました。
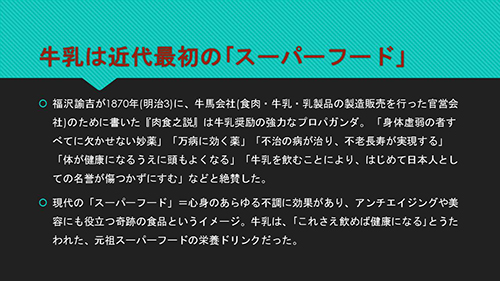
牛乳は近代最初の「スーパーフード」
このように明治初期には、牛乳の薬効に関する言説がどんどんヒートアップして、もはや何にでも効く奇跡の妙薬扱いになっていきます。
代表的な欧化論者の福沢諭吉は、食の西洋化のオピニオンリーダーとしても活躍しました。牛乳に関しても、奨励のキーパーソンでした。彼が明治3年に書いた「肉食之説」というパンフレットでは、「身体虚弱の者すべてに欠かせない妙薬」「万病に効く薬」「不老長寿が実現する」「体が健康になる上に頭もよくなる」と、過剰なまでの表現で絶賛しています。現代では法律に抵触するレベルの誇大広告です。
あたかも万能薬のように、これさえ食べれば、あるいは飲めば、あらゆる病気が治って健康になると謳う健康食品は、最近、「スーパーフード」という呼ばれ方をしています。
このように、知識人による華々しいプロパガンダを引っ提げて登場した牛乳は、これさえ飲めば健康になると謳われた「元祖スーパーフード」の栄養ドリンクだったと私は考えています。
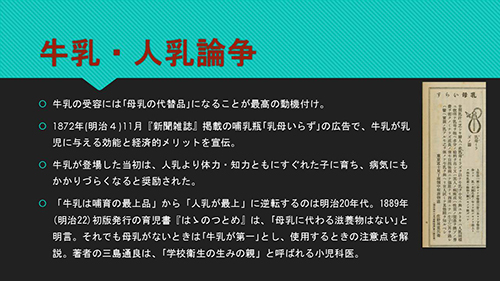
- 牛乳・人乳論争 -
赤ちゃんを育てるには人乳がいいか牛乳がいいかとは、牛乳が登場した当初から、重要な問題でした。
私が考えるに、牛乳批判が現在のようにいきおい感情的になり、敵視されがちなのは、嗜好品ではなく、母乳の代替品だったり、子どもの成長に必要な完全栄養食品に位置づけられたことが関係するのではないかと思ったりします。
あらかじめ、母性的な性格を付与されたがために、その期待に反したときの風当たりが必要以上に厳しくなって、攻撃が強くなるのではないかと思います。
先ほど言ったように、牛乳には肉食のような江戸時代からの連続性がありませんでした。そこで、超自然的な薬効に加えて、母乳のかわりに使えるというメリットが常に強調されて、受け入れるための重要な動機づけになりました。
明治天皇が牛乳を飲んだことを報じた「新聞雑誌」の同じ号の広告では、ゴムチューブの先に乳首がついたガラス製の哺乳瓶、その名も「乳母いらず」をイラスト入りで紹介して、母乳の少ない婦人はこの「乳母いらず」を使って牛乳を与えれば、母乳と同様に飲み、乳母に支払う給料と、乳母が病気にかかっていないか、賢い人かそうでないかを調べる労力を省けると、お得感を宣伝しています。
健康かどうかはともかくとして、どうして賢いかどうかが問題かといえば、お乳を通じて、授乳する人の性格、性質や精神状態が赤ちゃんに伝わって大きな影響を与えると考えられていたからです。
注目したいのはこのあと、「成長した後も自然と病気にかかりづらく、体力のある元気な子になる、西洋では生まれて3ヶ月も過ぎれば母乳が出ても牛乳を与える、日本人も試して効果を知るべし」と、やはり特殊な効能をアピールしていることです。
また、この宣伝が出る前の「新聞雑誌」にも、牛乳や乳製品で育てれば自然と根気が鍛えられて体も強くなるという記事が掲載されています。
このように、牛乳が登場した当初には、人乳より牛乳保育のほうがすぐれていると宣伝されました。それまでは母乳が出ない場合は、“すりこ”といって米の粉を湯で溶いたものや重湯を赤ちゃんに与えていたのですが、とても栄養が足りるはずはありません。動物の乳で人間の子を育てるという発想は、子育て革命だったわけです。
明治の育児書は翻訳書からはじまります。日本人による初の体系的な育児書は、明治22年に出版された「はゝのつとめ」だとされています。
著者の三島通良は小児科専門医で、初版を出したときはまだたったの23歳でしたが、その後、版を重ねて、育児の教科書的な存在になりました。この本は、国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができます。非常に実践的で、牛乳の選び方や火の入れ方や与え方について、微に入り細に入り、注意すべきポイントがとても丁寧に説明されていて、編集者的に見ても実用書の鑑のような本です。牛乳の選び方では、牛を飼っている牧場の面積や餌の種類にまで言及しています。
ここで三島通良は、母乳にかわる滋養物はないと、はっきり書いています。
それでもさまざまな事情で母乳がないときはやはり牛乳が第一ということで、細かく注意点が解説されていますが、一番重要としているのが哺乳瓶を清潔に保つことです。スライドにあるのが当時の哺乳瓶です。「乳母いらず」よりゴムの管が短くなっていますが、それでも完璧に滅菌するのは難しかい形ですね。
「はゝのつとめ」をきっかけに、日本人の書いた育児書が一気に世に出ました。ほとんどすべてが三島本を踏襲し、まず人乳が一番、やむを得ない場合は牛乳が一番、そして牛乳を使うときのノウハウという構成になっています。
牛乳俳斥論の台頭
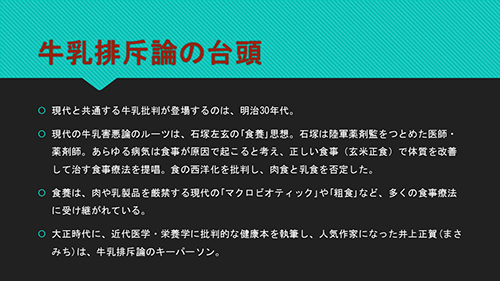
- 牛乳俳斥論の台頭 -
牛乳が最初から完全栄養食品だったとしたならば、それでは「牛乳害悪論」はいつから登場したかという問題です。
こうした賛美される健康食品には必ず反対意見が出るもので、人乳と牛乳の比較論は明治20年代から盛んになり、現代と共通する牛乳批判は明治30年代から登場しました。
その原点になったのは、石塚左玄が提唱した「食養」という食事療法です。
石塚左玄は、近代医学と薬学を学んで、陸軍で少将まで出世した医師兼薬剤師でしたが、明治維新以来の西洋崇拝と肉食礼賛の風潮を痛烈に批判しました。
明治30年代には思想の世界でも国粋主義が台頭してくる時代ですから、食の国粋主義と考えていいのではないかと思います。
石塚左玄の考えでは、あらゆる病気は食事が原因で起こり、正食(正しい食事)で体質を改善すれば、治る。人は風土に合ったものを食べるべきで、日本人は肉を食べる必要はないと、肉食と乳食を否定しました。
「食養」という食事療法は、牛乳、乳製品、肉類を厳禁している現在のマクロビオティックの直系の先祖で、現在あるほとんどの食事療法と民間療法に影響を与えています。
スローフード、地産地消という考え方のルーツでもありますし、日本で最初に食育を提唱した人とも言われています。
石塚左玄以外で牛乳有害説のキーパーソンだと私が考えているのは、井上正賀(まさよし)です。
井上はもともと農学博士で、大正時代に入ると、栄養の話や健康法、食事療法の一般向け啓発書を書きまくって、売れっ子作家になりました。今のマスコミ学者のはしりで、「中央公論」や「文藝春秋」などの論壇誌でも活躍しています。
大正時代は、それまで医学や生理学の一部だった栄養学が独立した学問として確立して、栄養研究所が設立されました。食べ物と健康との相関関係の研究が非常に盛んになった時代です。
この井上正賀が最大の標的にしたのが牛乳でした。井上はどの本でも、牛乳を論じるときは必ず最初に、「牛乳は本来、牛の子が飲むべきもので、人間には適さない」と主張します。
実は、現代の牛乳害悪論のキャッチフレーズに、「牛乳は牛の赤ちゃんが飲むもので、人間が飲むのは自然の摂理に反している」と、「乳は赤ちゃんが飲むもので、大人になっても乳を飲んでいるのは人間だけ」、この二つのパターンがあります。牛乳を否定する根拠としては余りに単純すぎるだけに、逆にインパクトが強く、「あっ、そうだったのか」とスッと心の中に入りやすい。これを使い出した元祖は、井上ではないかと私はにらんでいます。
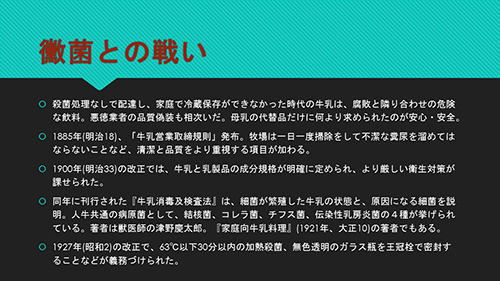
- 黴菌との戦い -
明治から戦前までの育児書を読んでいくと、人乳との優劣に増して、どの本でも、牛乳の鑑定法や選び方、消毒法、貯蔵の仕方、要するに安全性に多くのページが割かれています。逆に言うと、それぐらい不良品による健康被害が多かったのです。
流通と保存が未発達な時代の牛乳は、生産地と消費地が接近していることが絶対条件で、それでも腐りやすくて長くは置いておけないため、まだ暗いうちに搾ったものを朝に1回、午後に搾ったものを夕方に一回と、1日2回ないしは3回配達することが普通でした。
しかし、例えば東京の場合、赤坂あたりの牧場兼牛乳屋が深川まで遠路はるばる届けるなど、かなりの距離を、時間をかけて配達することも珍しくなかったので、特に夏場は腐敗のリスクと隣り合わせでした。
科学的知識のなかった初期の牛乳屋は、酸っぱくなったら砂糖を混ぜれば飲めると言ったり、凝固した牛乳はよく混ぜてから飲めと言ったり、危険な販売をしていたそうです。
牛乳の衛生対策のために「牛乳営業取締規則」が施行されたのが1885年(明治18年)でした。
しかし、結核のように人にも感染する病気にかかった牛の乳を搾ったり、牛乳に米のとぎ汁を入れてかさ増ししたり、傷んだ牛乳に薬物を入れてごまかしたりする悪徳業者も多かったようです。
牛乳は栄養豊富なだけに、ばい菌の温床になりやすいと、煮沸消毒の重要性がさらに強く説かれるようになったのは、1900年代、20世紀になってからです。
明治33年(1900年)に、より厳しい内容に改正された「牛乳営業取締規則」が公布され、翌年に「牛乳消毒及検査法」という専門書が発表されてから、育児書もそれにならって、牛乳のばい菌に対して敏感になっていきました。
これには北里柴三郎や志賀潔、野口英世など、日本の細菌学者たちの活躍も影響していると思います。
ヨーグルトが不老長寿の妙薬として登場して話題を集めたのは大正時代です。当時の有名な学者の中には、今の牛乳屋には細菌を試験する施設はないから、最初はよくても、ブルガリア菌をきちんと保存できるかどうか疑問を呈したり、雑菌が繁殖する危険があるので、不老長寿の薬と思って食べても恐ろしい伝染病にかかったり、発酵が腐敗に転じることもあると、警告しています。
冷蔵保存設備がない時代だったため、結局、ヨーグルトはブームにならずに自然消滅して、カルピスのように保存できる乳酸菌飲料が人気を得ました。
63度以下30分以内の低温殺菌が法律で定められたのは昭和2年です。家で沸騰させるより風味やビタミンなどの成分が保たれ、しかも細菌は死滅していると、消費者に歓迎されました。
それでも家庭用の冷蔵庫はまだまだ普及していなかったので、家に届いてからの状況はあまり変わらなかったでしょう。
このように、牛乳は不老長寿の妙薬として颯爽と登場して、さまざまな議論を呼びながらも、戦前までにかなり普及していました。
しかし、昭和15年11月から牛乳が配給制になって、母乳の足りない満1歳以下の乳児と病気の人だけに配給されるようになりました。
たんぱく質のカゼインを飛行機の接着剤に使うために、牛乳の増産が促されましたが、戦局が悪化するにつれて、牛を飼う飼料も労働力もなくなって、戦前までの牛乳文化は壊滅してしまいました。
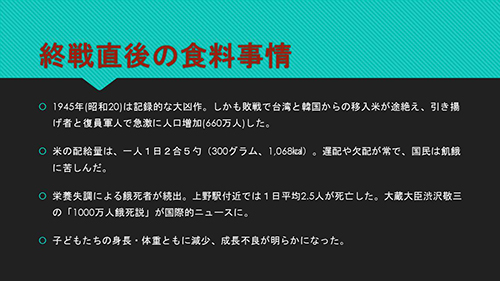
- 終戦直後の食料事情 -
そして戦後に入ります。終戦直後の食料事情がどうだったかというと、1945年の夏はまれに見る冷夏で、大凶作に見舞われました。その上、敗戦で、重要な米の供給地だった朝鮮と台湾からの米が入ってこなくなりました。なおかつ、海外にいた日本人と軍人が一斉に帰国しました。引き揚げ者と復員軍人の数は660万人です。人口が急激にふくれあがったのに、米が例年の半分くらいしかないという、まさに泣きっ面にハチ、ダブルパンチの悲惨さでした。
食糧難は戦中よりさらに悪化して、米の配給量は2合3勺、330グラムから30グラム減って300グラムになり、しかも配給が遅れること、なくなることがしょっちゅうでした。
おかずが少なく、米でほとんどのカロリーを摂る必要があるのに、300グラムの米からとれる熱量はたったの1,100キロカロリー弱しかありません。
配給の食糧では1,500キロカロリーがやっとで、実際はもっと低く、1,200キロカロリー程度だったという説もありますし、東京都民の場合は配給だけでは775キロカロリーしか摂れなかったという恐ろしいデータもあります。
都市部では栄養失調による餓死者が続出しました。上野駅付近の餓死者は1日平均2.5人、大阪では1日60人以上が亡くなりました。1,000万人が餓死をするという説が流れたくらいです。
悲惨だったのは食糧難の戦中戦後に成長期を過ごした子どもたちで、身長、体重ともにそれ以前よりずっと小さくなってしまいました。そこに登場した救いの神が、“ララ物資”の脱脂粉乳でした。